SHODAN -湘談-
「ベルマーレだからこそできることを」 ともに未来を描き、成長するパートナーシップ

KPMGコンサルティング株式会社 ×湘南ベルマーレ
2025.10.21
クラブを支えるパートナー企業との対談企画「SHODAN-湘談-」。今回のゲストは、デジタルイノベーションパートナーとしてクラブのデジタル変革をサポートしているKPMGコンサルティング株式会社の笹木亮佑アソシエイトパートナー。新たに立ち上げたサステナビリティ構想「BELL-BEINGプロジェクト」をはじめ、さまざまな取り組みを推進しています。同社におけるスポーツビジネスを牽引する笹木さんと坂本紘司代表取締役社長との対談は、クラブはもとより、国内のスポーツ産業の未来にまで想いを寄せるものとなりました。 以下敬称略
――KPMGコンサルティング(KPMG)は2020年に湘南ベルマーレのオフィシャルクラブパートナーとなりました。
笹木 はい。以来私たちは、「デジタルイノベーションパートナー」としてクラブのデジタル変革に伴走してきました。当初は2人だったスポーツビジネス専門人材も、いまでは25人規模にまで拡大しています。ベルマーレ様との取り組みは、当社のスポーツビジネスの原点です。JリーグやWEリーグをはじめ、沖縄県名護市とのご縁を活かしたアカデミー合宿の誘致など、広範な連携が実現しています。またスペシャルデーを通じた社員同士の交流や、アカデミーへの協賛による地域活性化など、ビジネス以外の面でも多くの取り組みを進めてきました。

なにより、私自身がベルマーレの大ファンで、5年前から関わらせていただき、いまでは家族全員で熱狂的なサポーターになりました。クラブスタッフとファン・サポーターの皆さんとの距離の近さは、Jリーグのクラブのなかでも随一だと思っていますし、湘南地域のため、ファンのために全力で走る選手たちの姿に、私は何度も心を動かされてきた。そうして、ベルマーレは常に私の心にあるクラブとなりました。
坂本 ありがとうございます。KPMGさんはクラブの未来をともに描き、ともに実行してくれる、単なるパートナーシップを超えた存在です。デジタルもサステナビリティも、理念だけでなく、実行フェーズまで伴走してくれる。ベルマーレにとって非常に心強い存在だと思っています。
――パートナーとなって、これまでどのような取り組みをされてきましたか?
笹木 第1回の湘談でも触れていますが、ベルマーレ様とまず取り組んだのがファンエンゲージメント、すなわちファンとの関係強化です。多くのスポーツクラブでは、顧客データが十分に活用されておらず、マーケティングは勘や経験に頼りがちです。そこで、どのチャネルから顧客が入ってきてもシングルIDでファンデータを統合できる仕組みを構築しました。次に、ポイント管理システムやキャッシュレス決済を導入し、顧客行動のデータを収集・分析することによって、顧客理解をより深めます。さらにAIを活用し、個々の価値観や嗜好を捉えることで、来場や購入の予測値を可視化し、お客様一人ひとりにパーソナライズしたマーケティングアクションを打っていく。このように、私たちはスタジアムを満員にすべく、まずはデジタルで仕組みを整えることを進めました。
坂本 我々はアナログな会社だったので、デジタルデータの活用は目から鱗でした。実際、その成果として、2023年にJリーグ加盟30周年事業の一環として実施した国立競技場でのホーム開催試合では、クラブ史上最多となる54,243人の入場者数を記録しました。デジタル技術は通常のホームゲームでも活用され、チケット売上や来場数、チケット単価の向上に寄与しています。

一方で、KPMGさんのありがたいところは、そういうノウハウを教えるだけにとどまらないこと。実行し、結果が出るところまで伴走してくれる。取り組みを始めた当初はまだ関わる人数は少なかったと思いますが、いまでは大勢でベルマーレの事務所までお越しいただいてミーティングをするなど、仕事の内容以上に私はKPMGの皆さんの人となりが好きになりました。
笹木 うれしいです。ともするとコンサルタントというのは、あるべき論だけ伝えていなくなるような存在に思われているのではないかと想像しますが、そのスタンスは違うと私は考えており、クライアントと一緒に泥水をすすり、伴走して、そのうえで最終的にコンサルタントはいなくなっていいものだと考えています。なぜなら、クラブがしっかり自走していくこと、それこそがスポーツ界の発展に繋がると考えるからです。いまお話ししたファンエンゲージメントも、今年から我々の関与度をぐっと下げたフェーズに入ってきている。ベルマーレ様も私たちも、ともに成長していくことが理想的なパートナーシップだと思っています。
――先ほど、ベルマーレとの取り組みはJリーグやWEリーグなど他クラブとの連携にも広がっているというお話がありました。詳しく伺えますか?
笹木 はい。ベルマーレ様と取り組みを推進していくなかで、これまで多くのマーケットへのインサイトを発信してきました。取り組みの内容について教えてほしいと、JリーグやWEリーグから問い合わせがあったことがきっかけです。国内のスポーツ産業が潤っていくことが私たちの実現したい世界観なので、ベルマーレ様と構築したモデルをリーグに持っていき、リーグから各クラブに落とし込んでもらうのが最もスムーズだと考え、いま実際に進めているところです。
加えて、行政への広がりもありますね。「スポーツ×街づくり」という文脈のなかで、プロスポーツチームの活性化をテーマにしている地域があり、自治体からアドバイスを求められる機会も増えています。
ベルマーレ樣は我々のスポーツ案件第1号です。スポーツのフィールドをご提供いただき、失敗もたくさんしながらつくり上げていったものが、いま私たちのサービスとして世に提供できている。とても感謝していますし、ベルマーレ様があるからいまの当社のスポーツビジネスがあると考えています。
坂本 ありがたいです。
――ファンエンゲージメントのほかに、取り組んできたことはありますか?
笹木 もう一つの柱として共創しているテーマは「クラブのサステナビリティ経営」です。ベルマーレ様はこれまでも「COPA BELLMARE」や「LEADS TO THE OCEAN(通称LTO)」など、Jリーグトップレベルで様々な活動を精力的に行ってきました。そのうえで、それらのアクションを単体ではなく、ベルマーレ様が目指すビジョンとして誰もが分かる形に束ねていく必要性を感じ、昨年、新たなサステナビリティ構想「BELL-BEINGプロジェクト」をベルマーレ様とともに創り上げました。
坂本 実際、クラブとして地域貢献活動やパートナー企業との協働には、これまでも何度も取り組んできました。
ただ、その一つひとつがどう繋がっているのか、そして何のためにやっているのかが分かりにくかったんです。言い換えると、「点」で終わっていたんですよね。
そこで、私たちは活動の“目的”を明確にする必要があると感じました。
参加してくださる企業や団体の皆さんにとっても、そしてクラブスタッフにとっても、どこを目指しているのかを共有できることは非常に大事だと思います。
BELL-BEINGプロジェクトは、まさにそうした課題意識から生まれた取り組みです。
「スタジアムで生まれる熱狂や感動を、どう地域の日常へと広げていくのか」。
「ベルマーレがあることで、地域にどんな良いことがあるのか。」
そのための“仕組み”をクラブとして本気で作りたい、という想いが根底にあります。
スタジアムで味わうあの一体感を、ホームタウン地域や学校、行政、企業、そして暮らす人々にも広げていきたい。
「スタジアムでの勝利のダンス」を、ホームタウン地域の様々な場所に広げていきたいと考えています。
――どのようなステップを踏んだのでしょうか。
笹木 クラブが社会にどう貢献していくのか、その理想像と道筋を描いた戦略づくりとして「サステナビリティストーリー」の策定を支援しました。まずはこれまでの活動や湘南地域の課題を基にクラブの皆さんと議論を重ね、ステークホルダーと重要テーマ(マテリアリティ)を特定。次に短期・中期・長期の時間軸で、クラブが目指す姿と各テーマで提供する価値を整理しました。それらを一枚の絵にまとめたのが「BELL-BEINGロードマップ」です。これは「Bellmare×Well-Being」の造語で、クラブのありたい姿とそこに至る道筋を示す、事業・サステナ推進の軸となるものです。さらに、活動の社会的価値を貨幣価値換算して定量評価する「インパクトマップ」を提供しました。これにより、クラブの取り組みがどれだけの社会的インパクトを生み出しているかを具体的な数字で示すことが可能になりました。
そして現在は、自治体や企業とクラブがともにアクションを起こす「価値共創プラットフォーム」を展開しています。これを通じて、スポーツを起点に地域・企業・ファンが一体となって社会課題に向き合う。そんな未来をベルマーレ様とともに描いています。
坂本 このストーリーは、クラブの理念を形にするだけでなく、実際の活動に落とし込むための指針で、社内ワークショップや営業資料、特設サイトなど、KPMGさんと一緒に実行フェーズまで設計しています。
特設サイト:サステナビリティ|BELL-BEING PROJECT >
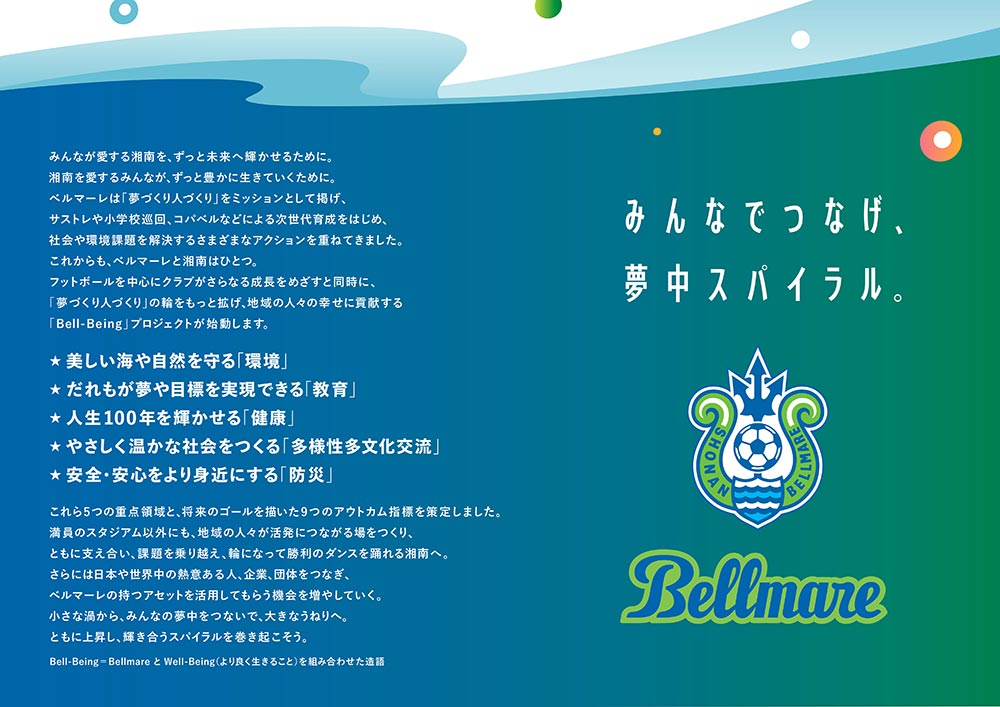

笹木 こうしたサステナビリティ活動は、クラブに社会貢献の精神で向き合う素地がないとできないものです。その点、ベルマーレ様にはこれまでの取り組みが裏付けるように、十分な素地がありました。一方で、活動を続けていく際に、ボランティアだけでは限界があると私は思っています。それを考えたときに、ベルマーレ様が掲げているテーマを整理し、この活動に協賛してもらえる仕組みをつくらないといけない。企業に対し、いままでは単に広告費だったものを、教育や採用のための人材開発の費用といった形で提案できるようにしたい。サステナビリティ活動をサステナブルにやる仕組みをつくりたいという想いがありました。
坂本 実際、「BELL-BEING」はクラブだけで実現できるものではありません。ファン・サポーターや地域の皆さんに積極的に参加していただきたいですし、自治体とも地域の課題解決に向けて活発に連携していきたい。そして企業には、BELL-BEINGパートナーとしてファン、スタジアム、コネクション、発信力といったクラブのアセットを活用して活動に参加したり、その企業独自の活動を実施したり、社会的価値を共創してもらいたいと考えています。
笹木 地域のシンボルであり、公共性の高いクラブであるベルマーレ様だからこそ実現できる取り組みがあります。企業にとっても、クラブと一緒に社会課題に取り組むことで、自社の価値向上に繋げることができる。さらにクラブをハブにすることで、1社だけでなく複数の企業が連携・共創し、より大きな社会的インパクトを生み出すことが可能になる。ベルマーレ様の特徴は、活動を「やって終わり」にせず、その社会的な成果を定量的に測定している点です。私たちはその仕組みづくりを支援し、どれだけの価値が生まれたのかを「見える化」しています。
――「BELL-BEING」活動について、具体的な事例もお聞かせください。
坂本 一つは「スポーツの価値と可能性を考えるワークショップ」です。これはスポーツの未来を担う若者たちに、スポーツ産業の可能性を伝えることを目的に始まりました。クラブのパートナー企業が集まり、高校生や大学生を交えて、最先端のテクノロジーや社会課題との向き合い方など、スポーツを通じて社会をどう変えていけるかを語り合う場です。

笹木 「スポーツの価値と可能性を考えるワークショップ」は単なる講演会ではなく、双方向の対話と探求の場として設計しました。学生たちは、企業のリアルな取り組みを知り、自分たちのキャリアや社会との関わり方を考えるきっかけを得ることができます。企業側も若者の視点から新しい発想や価値観を受け取ることができる、まさに共創の場です。イベント後にはアンケート調査を実施し、どれだけの学生がキャリア意識を持つようになったかを分析しました。さらに採用コストや人材定着率などの指標を活用し、社会的インパクトを貨幣価値に換算しました。これにより、企業にとっても継続的な投資価値がある取り組みとして認められ、2023年から3年連続で開催に至っています。
坂本 スポーツクラブがこうした教育の場を提供するのは、Jリーグのなかでも珍しい取り組みです。ベルマーレが地域の「学びのハブ」になることで、若者の未来にポジティブな影響を与えられると確信しています。
笹木 「お仕事紹介フェア」の活動も幅が広がっていますね。これは地域の雇用課題に真正面から向き合う取り組みです。湘南地域では、地元企業の認知度不足や若年層の地元離れが課題となっていて、企業の採用活動が思うように進まないという声を多く聞いていました。そこでベルマーレ様と一緒に、地元で働くことの魅力を伝える場として「お仕事紹介フェア」を企画しました。参加企業には、単なる「採用ブース」ではなく、「地域に根ざした企業としての社会的価値を伝える場」として出展していただきました。

坂本 クラブがハブになることで、企業と地域住民、求職者を繋ぐことができる。これはスポーツクラブだからこそ提供できる価値だと思っています。地域の方々からも「地元企業のことを初めて知った」「働いてみたいと思った」といった声をいただきました。
笹木 仮にベルマーレファンの私が仕事を探す立場になったら、自分が応援しているチームをその企業がサポートをし、会社にベルマーレのロゴがあればワクワクもします。これができる業態は限られるので、すごく価値のあることに取り組んでいると実感することができます。
坂本 私もブースを回りましたけど、出展された企業の皆様にとても喜んでいただきました。参加企業も去年は2社、今年は6社と増えているので、今後もっと広がりが出てくるのではないかと感じています。
笹木 お子さん連れのご家族も多かったですよね。
坂本 そうですね。会社説明会とは違い、スポーツを観に来た方が気軽にふらっと立ち寄れるのがいいですよね。また、あるブースに来た方が「ちょうどこれ欲しかったので、今度商談させてください」とおっしゃって、その場でビジネスに繋がったという話も聞きました。
笹木 そんなことがあったのですね!
坂本 アウェイサポーターの方も立ち寄られたそうですし、スポーツの場ならではの効果だと感じますね。
笹木 そうですね。イベント後には参加者の行動変容や企業認知度の向上をアンケートで分析し、採用コスト削減効果や地域経済への波及効果を定量化しました。これにより、企業にとっても「社会的価値を生む採用活動」としての意義が明確になり、継続的な参加に繋がっています。
坂本 そして直近では「サステナトレセンProject.」の活動も力強く推し進めています。この活動は「世界はたのしく変えられる。」を合言葉に、地域の次世代を担う子どもたちに、サステナビリティを「学び・描き・混ざり・動く」というプロセスで体験してもらう教育プログラムです。半年間にわたり、学校の授業のなかで子どもたちは地域の課題を学び、「この街に住み続けたくなる」アイデアを考えます。そして、そのアイデアを企業と一緒に形にしていく。まさに探求型の実践学習です。

笹木 この取り組みの素晴らしい点は、アイデアを実装するリアルな場があることです。たとえば、6月の町田戦で販売された「地産地消カレー」。これは子どもたちがサステナトレセンで考えたメニューを実際に地元企業と連携して商品化したものです。しかも、ただ販売するだけでなく、環境負荷を減らす工夫も盛り込まれている。地元産の食材や太陽光発電による電力、リユース容器の使用など、CO₂排出削減に配慮した設計です。私たちは、これらの施策によるCO₂削減量の算定を支援し、どれだけの環境貢献があったかを「見える化」しました。これにより、参加者や来場者の行動変容にも繋がり、教育と実践、そして社会的インパクトの可視化が一体となった先進的なサステナビリティアクションになったと考えています。

坂本 お話を伺っていると、笹木さんたちのお仕事は、私たちが抱いているイメージをより確かに言語化したり数値化したりすることのように思いますね。
笹木 そうかもしれないですね。クライアントの意図を明確にするというか、言語とツールを使って、取り残すことなく皆さんの目線を合わせることを大事にしていると言えるかもしれません。
坂本 地域にとっていいことだと思って活動していても、それを検証できなければ継続しないですよね。実行する我々がきちんと理解し、効果を実感して、だから「来年も再来年もやれるよね」と思えるように効果を測定する重要性を示して、学ばせてもらっていると感じます。
笹木 ありがとうございます。いまお話ししたこれらの事例は、すべて「BELL-BEING」の理念を具体的に体現したものです。クラブが社会課題に向き合い、企業や地域とともに価値を創出し、そのプロセスを設計・実行・測定・改善まで一貫して行うことで、持続可能な仕組みになっている。共創していただける企業が増えるほど、参加していただく皆さんにとっても、社会にとっても価値のあるものになります。私たちも改善を重ねながら、企業、サポーター、地域の皆様にとって魅力的な場を、ベルマーレ様と関係する皆様と一緒につくり続けていきたいと思います。

―――今後どのような取り組みを考えているか教えてください。
坂本 今年11月には、「BELL-BEINGデー」をホームゲームで開催予定です。これは、クラブが策定したBELL-BEINGロードマップを体現する場として、サポーターや地域の皆さんが楽しみながら学び、体験できるイベントです。スタジアムが単なる試合観戦の場ではなく、地域の未来を考える場になる。そんな新しい価値を提供したいと考えています。
笹木 ベルマーレ様と一緒に取り組んできた内容は、プロスポーツクラブとしては類を見ない先進的な事例です。これらの取り組みは、他クラブにも広がるべきであり、我々としても、全国のスポーツチームに展開していく責務があると感じています。スポーツは単なるエンタメではなく、社会課題解決のプラットフォームになり得る。その可能性を最大限に引き出すために、私たちは引き続き、クラブのブランディング支援や仕組みづくりに尽力していきます。
また「BELL-BEINGデー」は当社のスペシャルデーでもあります。スペシャルデーは当社にとって一大イベントで、社員とその家族を合わせると毎年500人以上が来場します。社員皆が楽しみにしているイベントですし、ベルマーレ様との取り組みを社内に発信できるよい機会となっています。
坂本 KPMGさんは団結力があって、仲が良いですよね。デジタル的なイメージが先行しがちですが、人間味あふれる部分をすごく感じますし、そこが何より大好きです。
―――ベルマーレとのパートナーシップを今後どのように深めていきたいか、最後にお聞かせください。

笹木 先ほども話に出ましたが、我々としては、ベルマーレ様だからこそできることを大事にしていきたいと考えています。湘南地域に根付いたベルマーレだからこそ生み出せる社会価値をしっかりと言語化、定量化して世の中に伝えていくことを今後も続けていきたい。
あとはやはり「共創の輪」ですね。ベルマーレ様という最高のプラットフォームのなかで、関係する人や企業、行政、ファン・サポーターの方々が、試合の勝敗に関わらず、常に社会のために行動し続けているという世界観を私たちはつくっていきたい。これもまたベルマーレ様だからこそできることだと思っています。こういったモデルケースをどんどんつくり、最終的には社会価値と経済価値を両立させた状態でクラブ運営が実現し、国内のスポーツ産業が豊かに発展していくことが我々の大きな目標であり、使命だと考えています。今回の対談を通じて、ベルマーレ様のこれまでの実績と挑戦はスポーツクラブの新たな役割を体現するものであり、私たちKPMGもその挑戦に引き続き伴走していきたいと、あらためて強く思いました。
坂本 非常に心強いです。KPMGさんとの取り組みはクラブの可能性を広げるものであり、とても価値がある活動です。これからも、地域、企業、ファン・サポーターの皆さんと一緒に、「BELL-BEING」の実現に向けて歩み続けたいと思います。


 過去のSHODAN-湘談-はこちら
過去のSHODAN-湘談-はこちら